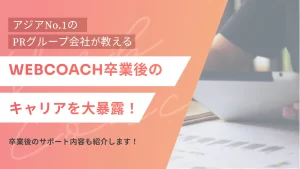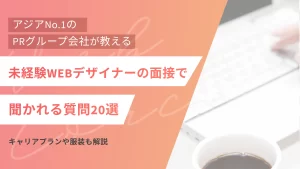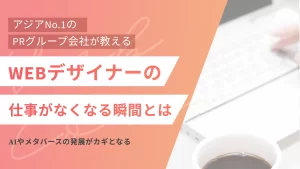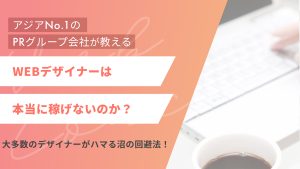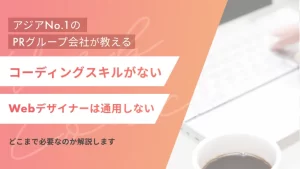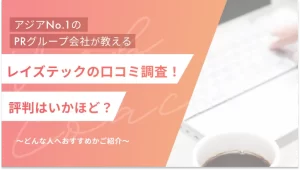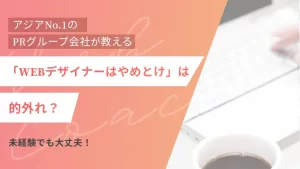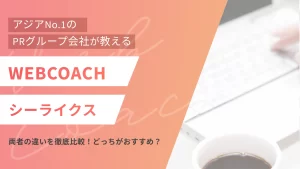現役デザイナーが教えるおすすめのWEBデザインツール10選!選び方や使いこなすコツを徹底解説
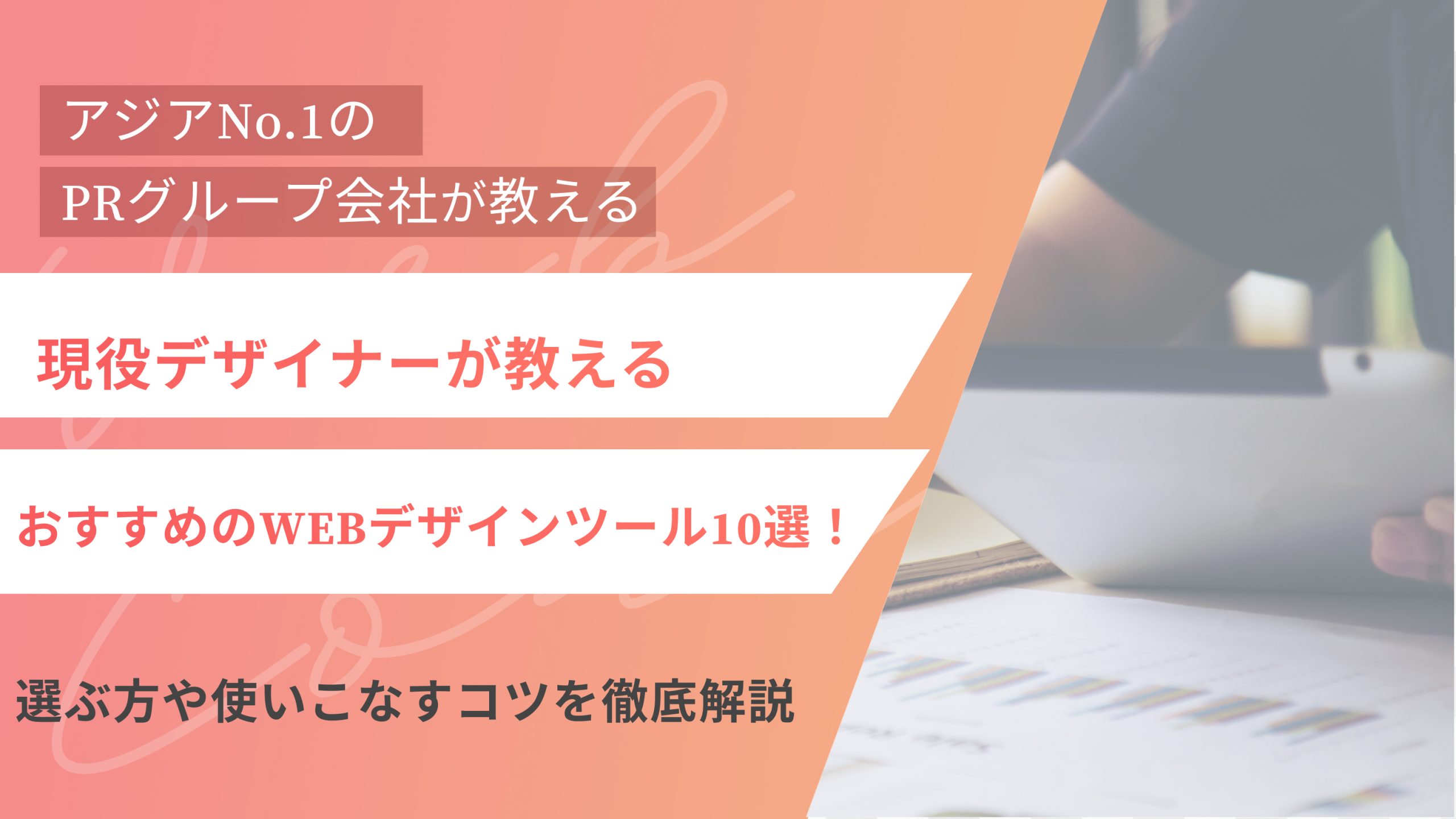
WEBデザイナーを目指して学習を始めると、Figma、Adobe XD、Photoshopなど、数多くのツールがあり、「一体どのツールから手をつければいいの?」「利用するツールは一つだけでいいの?」と混乱してしまいますよね。
時間やお金をかけて学んだツールが、数年後には時代遅れになるような失敗は絶対に避けたいはずです。
結論から言うと、WEBデザインツールは目的によって使い分けるのが基本ですが、未経験からWEBデザイナーを目指すなら、「Figma」「Canva」「Adobe XD」「Miro」「Balsamiq」のツールから始めることをおすすめします。
また、すでにWEBデザインに触れていてある程度ツールにも慣れている方は「Photoshop」「Illustrator」「Google Web Designer」「Sketch」「Krita」がおすすめと言えます。
この記事では、現役WEBデザイナーが各種ツールの特長を踏まえ、以下の点を徹底解説します。
- WEBデザインツールでできること
- 未経験者・経験者それぞれにおすすめのWEBデザインツール10選
- WEBデザインツールの使い分けマニュアル
- WEBデザインツールを選ぶ際の注意点
- WEBデザインツールを使いこなすコツ
ただし、自分に最適なツールや学習の順番が分かっても「本当にこの方法で転職できるだろうか」「一人で学習を続けるのは不安」と感じる方も多いはず。
未経験から転職するには、あなただけの学習ロードマップが欠かせません。
もし、あなたに最適な学習プランやキャリアについて少しでも相談してみたいと感じたら、ぜひ一度、無料カウンセリングにお越しください。
不安を解消し、最短でWEBデザイナーになるための道筋を提案します。
WEBデザインツールとは?
WEBデザインツールとは、WEBサイトの見た目UIやレイアウトを設計・作成するためのソフトウェアです。
コーディングを始める前に、サイト全体の完成イメージを視覚的に作り上げ、デザインの方向性を固めるために使用されます。
主な機能として、テキストの配置や配色、画像の挿入などを通して、WEBページの見た目を自由にデザインできます。
また、多くのツールには「プロトタイピング機能」が搭載されており、ボタンをクリックした際の画面遷移など、実際のサイトに近い動きをコーディングなしで再現することが可能です。
ただし、ツールの特性を理解しておくことが重要です。
- 求められる知識レベルは様々:多くのツールではコーディングの知識がなくてもデザインを作成できるが、中にはHTML/CSSの知識が求められるツールも存在する。
- 操作性はツールによって異なる:初心者向けのツールは直感的に操作できるものが多い一方、プロ向けの多機能なツールは、すべての機能を使いこなすために一定の学習時間が必要。「多機能=誰にとっても使いやすい」というわけではない。
- 共同編集・共有機能の有無:近年のデザイントレンドとして、FigmaやAdobe XDのように、チームでの作業効率を上げる「共同編集機能」や「共有機能」を備えたツールが主流になりつつある。しかし、すべてのツールにこの機能が搭載されているわけではないため、特にチームでの制作を想定する場合は、ツール選定の際に重要な確認項目となる。
このように、WEBデザインツールは単に見た目を作るだけでなく、制作プロセス全体の効率化に貢献する、現代のWEBデザイナーにとって不可欠な道具と言えるでしょう。
WEBデザインツールでできること
WEBサイト制作のデザイン工程において、具体的に「何ができるのか」を4つの主要な機能に分けて解説します。
| できること | 詳細 |
|---|---|
| ワイヤーフレーム作成 | ワイヤーフレームとは、WEBサイトの骨格やレイアウトを決める「設計図」のこと。ユーザーの行動を意識した情報設計の土台となる、非常に重要な工程で、このツールを使うことで効率的に作成できる。 |
| ビジュアルデザイン作成 | 配色、フォントの選定、画像の配置などを行い、最終的な完成形に近い見た目(UIデザイン)を作り上げる機能。WEBサイトの印象を決定づける中心的な作業と言える。 |
| プロトタイピング | 作成したデザインにリンクやアニメーションを設定し、実際のWEBサイトのように操作できる「試作品」を作る機能。これにより、公開前に使いやすさを検証し、デザインの質を高めることができる。 |
| 共同編集・共有 | 複数のデザイナーがリアルタイムで一つのファイルを編集したり、エンジニアやお客さまにデザインデータを共有したりする機能。チームで開発を行う上で、作業効率を飛躍的に向上させるために不可欠な機能と言える。 |
| コーディング支援 | デザインデータからHTML/CSSコードを自動生成したり、開発者向けの仕様書を出力したりする機能。ツールによって精度や実用性に差があるため、そのまま実装に使えるかは確認が必要。 |
目的やスキルレベルに応じてツール使い分けることで、デザイン業務の効率と品質を高めてくれます。
自分に合ったツールを選び、継続的に使いこなすことで、WEBデザイナーとしての成長と年収アップにもつながるでしょう。
できることがわかったところで、次にWEBデザインにおすすめのツールを10選紹介します。
経験者・初心者別に分けて、おすすめのツールを紹介するので参考にしてください。
経験者におすすめのWEBデザインツール5選
ここでは、デザインの基礎を理解し、さらなる専門性を追求したい経験者の人におすすめのツールを5つ紹介します。
これらはWEBデザイン業界で長年の実績がある定番ツールや、特定の分野に特化したプロ向けのツールです。
| ツール名 | 主な用途 | 料金 | 無料期間 | 対応OS |
|---|---|---|---|---|
| Photoshop | 写真加工、画像編集、バナー制作、LPのメインビジュアル制作 | フォトプラン:1,188 円/月 | 7日間 | Windows, macOS, iPadOS |
| Illustrator | ロゴ、アイコン制作、イラスト制作、印刷物デザイン | 単体プラン:3,828 円/月 | 7日間 | Windows, macOS, iPadOS |
| Google Web Designer | HTML5ベースのアニメーション広告、インタラクティブコンテンツ制作 | 無料 | 無料 | Windows, macOS, Linux |
| Sketch | UI/UXデザイン、WEBサイト・アプリのデザイン | スタンダード:9ドル〜/月 ビジネス:20ドル/月 | 30日間 | macOS |
| Krita | デジタルペイント、イラスト制作、テクスチャ作成 | 無料 | 無料 | Windows, macOS, Linux |
Photoshop
Photoshopは、WEBサイトのビジュアル作り込みや、写真の加工・補正において高い性能を発揮するグラフィック編集ツールです。
多くの機能を備えているため習熟には時間が必要ですが、使いこなすことで、よりクオリティの高いビジュアル表現が可能になります。
- FigmaやXDでのデザイン経験があり、さらにグラフィック表現を強化したいWEBデザイナー
- LPのキービジュアルや広告バナーなど、ビジュアルの訴求力が重視される案件を専門にしたい人
- レタッチや画像合成など、グラフィック制作の専門スキルを身に付けたい人
レイヤーマスクや調整レイヤーを用いた非破壊編集、複雑な切り抜き、多彩なフィルター効果といった機能は、リッチなグラフィック制作には欠かせません。
特に、細部のクオリティが求められる広告バナーやブランドサイトのキービジュアル制作において、その性能が最大限に活かされます。
これらの専門的なスキルは、デザイナーとしての対応範囲を広げる上で強みとなるでしょう。
Illustrator
Illustratorは「ロゴも作れる」「印刷物も対応できる」という付加価値を身に付け、デザイナーとしての対応領域を戦略的に広げるためのツールです。
独自の操作性は学習コストが高いものの、Webとリアルを横断するブランディング案件に対応できる希少な人材になれる可能性があります。
- WEBデザインと並行して、企業のロゴやサービスアイコンの制作も請け負いたいデザイナー
- WEBサイトとパンフレットなど、オンラインとオフラインを横断したブランディング案件に携わりたい人
- インフォグラフィックなど、図解を多用するコンテンツ制作を得意としたい人
ペンツールなど独自の操作概念は習熟に時間を要するため、初心者にはハードルが高いかもしれません。
しかし、一度マスターすれば、あらゆるサイズ展開に対応できる高品質なロゴやアイコンを作成可能です。
また、印刷で用いられるCMYKカラーに対応できるため「WEBも印刷物も、一貫した品質で任せられるデザイナー」として信頼が高まり、活動領域が大きく広がるでしょう。
Google Web Designer
Google Web Designerは「動きのある広告を制作できる」という専門スキルを掛け合わせ、自身の市場価値を明確に差別化するためのツールです。
静的なデザインとは全く異なるスキルが求められますが、広告という成果に直結する分野で専門性を高めたい経験者の人にとって最適と言えます。
- WEB広告代理店や事業会社のインハウスで、ディスプレイ広告の制作・運用スキルを高めたいデザイナー
- 静的なバナー制作から一歩進んで、アニメーションを用いたリッチな広告表現を身に付けたい人
- WEBマーケターとしてのキャリアも視野に入れているデザイナー
このツールは、一般的なWEBデザインツールと異なり、タイムラインベースのアニメーション制作という独自のスキルが求められます。
Google広告との連携もスムーズで、制作から入稿までのワークフローを劇的に効率化でき、扱えるデザイナーはまだ少ないため、希少価値が高いスキルと言えるでしょう。
Sketch
Sketchは、主要ツールであるFigmaに加え、「Sketch案件にも対応可能」という対応力の幅広さを示すためのツールです。
経験者として参画できる案件の選択肢を増やし、歴史あるプロジェクトで活躍するチャンスを得るための「戦略的スキル」として推奨します。
- スタートアップやIT企業など、長年Sketchをデザイン基盤としてきた組織のプロジェクトに参画したいMacユーザーのUI/UXデザイナー
- 大規模なデザインシステムがSketchで構築されている現場で、過去のデザイン資産を扱える必要がある人
新規でUIデザインを学ぶならFigmaが第一候補であり、Sketchの操作習得は必須ではありません。
しかし、Figma登場以前から続くサービスや大規模なデザインシステムでは、Sketchが標準ツールとして指定されている現場がいまだに存在します。
こうした案件に対応できることは、他のデザイナーにはない強みとなり、自身の対応力を証明する武器となるでしょう。
Krita
Kritaは、イラスト制作に特化した無料のペイントツールで、WEBデザインに手描きのイラストを取り入れたい場合に役立ちます。
一般的なWEBデザインツールとは操作性が異なるため、イラスト制作の知識やスキルが必要ですが、オリジナリティのあるデザイン表現を目指す上で便利ツールとなるでしょう。
- 自身のWEBデザインに、温かみのある手描きのイラストや独自のテクスチャを取り入れたいデザイナー
- WEBデザインだけでなく、イラストレーターとしての活動も視野に入れているクリエイター
- 外注コストをかけずに、サイトのメインビジュアルや挿絵を自作したい人
このツールは、UIデザインツールとは思想も操作性も全く異なり、イラスト制作の基礎から学ぶ必要があります。
しかし、豊富なブラシや手ブレ補正といったイラスト制作に特化した機能を活用することで、テンプレート感のない、ユニークなデザインを生み出すことが可能です。
イラストを自作できるスキルは、他のWEBデザイナーとの差別化要因となり、クリエイターとしての価値を大きく高めるでしょう。
初心者におすすめのWEBデザインツール5選
ここでは、これからWEBデザインを学ぶ未経験者の人が、挫折せずに楽しく学習を始められるツールを5つ紹介します。
選定基準は「無料で始められるか」「操作が直感的か」「学習情報が豊富で、かつ将来性があるか」の3点を重視しました。
| ツール名 | 主な用途 | 料金 | 対応OS |
|---|---|---|---|
| Canva | SNS投稿画像、プレゼン資料、簡単な印刷物のデザイン | 無料〜 | Windows, macOS, iOS, Android(ブラウザ版もあり) |
| Figma | UI/UXデザイン、Webサイト・アプリのデザイン、プロトタイピング | 無料〜 | Windows, macOS, Linux, ChromeOS(ブラウザ版もあり) |
| Adobe XD | UI/UXデザイン、プロトタイピング | 無料〜 | Windows, macOS |
| Miro | オンラインホワイトボード、ワイヤーフレーム作成、情報設計 | 無料〜 | Windows, macOS, iOS, Android(ブラウザ版もあり) |
| Balsamiq | ワイヤーフレーム作成(手書き風) | 無料〜 | Windows, macOS, Linux(ブラウザ版もあり) |
Canva
Canvaは、デザインの専門知識がなくても、プロが作ったようなデザインを短時間で作成できる「テンプレート」が圧倒的に豊富なため、最初の第一歩としておすすめです。
AIによるデザイン自動生成機能「Magic Design」なども搭載されています。
- デザイン完全未経験の入門者
- 本業はデザイナーではないが、業務でSNS投稿画像や簡単な資料作成が必要なビジネスパーソン
WEBデザインの専門ツールではありませんが、豊富なテンプレートに触れることで「見やすいレイアウト」や「心地よい配色」のパターンを感覚的にインプットできます。
本格的な学習前の「デザインに慣れる」「デザインを楽しむ」という最初のステップとして最適です。
Figma
Figmaは、WEB制作現場で「共通言語」となっている圧倒的な業界シェアと、未経験者の学習コストを限りなくゼロに近づける強力な無料プランが存在するため、最もメジャーでおすすめなツールです。
- 実務未経験から、本気でWEBデザイナーへの転職・就職を目指すすべての初心者
- WEBデザインツールの中でもメジャーなツールを使用したい人
- 将来的にフリーランスとして場所を問わず働きたい人
ほとんどのWEB制作会社の求人で「Figmaスキル必須」とされており、習得が直接的に採用に結びつく可能性が高いです。
また、ブラウザーベースで動作するためパソコンのOSを問わず、共同編集機能を通じてチーム開発のフローを実務に近い形で学べる点も、転職を目指す上で大きなアドバンテージとなるでしょう。
Adobe XD
Adobe XDは、Adobe Creative Cloud製品との連携を活かしたプロトタイピングツールです。
ただし、2023年にアップデートが停止され、Adobeは新規プロジェクトでのFigma使用を推奨している状況です。
- 既存のXDで制作されたプロジェクトの維持・更新を担当する人
- 短期的なプロジェクトで、既にAdobe Creative Cloudライセンスを持っている人
- シンプルなプロトタイピングのみを必要とする小規模な案件を扱う人
Adobe XDの主な機能として、PhotoshopやIllustratorで作成した素材をコピー&ペーストで取り込める連携機能があります。
リピートグリッドによる反復レイアウトの効率化や、画面遷移の自動アニメーション機能も利用できます。
ただし、現在は以下の点に注意が必要です
- 新機能の追加やバグ修正が行われない
- チーム機能や共有機能がFigmaと比べて限定的
- 将来的なサポート終了のリスク
- 採用企業が減少傾向にあり、転職時にスキルとして評価されにくい
既存プロジェクトの継続や、Adobe製品に慣れ親しんだ環境での短期利用には適していますが、新規学習や長期的なツール選択としては、業界標準となっているFigmaを優先的に検討することをおすすめします。
Miro
Miroは、WEBサイトの見た目を作る前に、頭の中のアイデアを整理し、サイトの骨格を考える「デザインの土台作り」を、楽しく視覚的に学ぶためのツールです。
いきなり綺麗なデザインを作るのが難しいと感じる初心者の人に、最初のステップとして最適です。
- デザインの「考え方」や「情報の整理術」からしっかり学びたいと思っている人
- いきなりデザインを始める前に、まずは頭の中をスッキリ整理したい人
- サイトのページ構成(サイトマップ)や、ユーザーがどう動くか(ユーザーフロー)といった、Webデザインの「設計図」作りを体験してみたい人
Miroは、無限に広がるオンライン上のホワイトボードに、付箋を貼ったり、文字や図を書いたりする感覚で直感的に使えます。
例えば、「どのページにどんな情報を載せるか」を付箋で書き出してグループ分けしたり、「このボタンを押したらどのページに飛ぶか」を矢印でつないだりする訓練が可能です。
綺麗なビジュアルを作るだけでなく、こうした「なぜこのデザインにしたのか」という設計の過程をMiroで見せることは、就職・転職活動で大きなアピールポイントになります。
Balsamiq
Balsamiqは、デザイン学習で初心者が陥りがちな「色やフォント選びに夢中になって、肝心のレイアウトが決まらない」という悩みを解決し、WEBサイトの骨格(ワイヤーフレーム)作りに集中するためのツールです。
あえて装飾機能を削ぎ落とした、いわば「レイアウト練習専用ツール」と言えます。
- つい細かいデザインに気を取られてしまい、全体の構成を考えるのが苦手な人
- とにかくシンプルな道具で、頭の中のアイデアをサッと形にしたい人
- 本格的なビジュアルデザインに進む前に、Webサイトの「良い配置」のパターンをたくさん身に付けたい人
Balsamiqの最大の特徴は、まるで紙に手でスケッチしたような、温かみのある「手描き風」のデザインにあります。
これにより、「うまく見せなきゃ」というプレッシャーから解放され、純粋に情報の配置や使いやすさだけを考えられます。
機能はボタンやテキストボックスといったパーツを配置するだけの非常にシンプルなものです。
操作に迷うことがほとんどないため、アイデアが浮かんだらすぐにレイアウト作りの練習に取り掛かれます。
WEBデザインツールの使い分けマニュアル
プロのデザイナーは、1つのツールですべてを完結させるのではなく、制作物の目的や作業フェーズに応じて複数のツールを使い分けています。
なぜなら、各ツールには得意・不得意があり、適材適所で活用することで、制作の質と効率を最大化できるからです。
ここでは、各WEBデザインツールの使い分け方について解説します。
Figma・XD:共同編集やWEB設計に最適
FigmaやXDは、WEBサイトやアプリのUIデザイン、つまりユーザーが直接触れる画面の見た目や操作性を設計することに特化したツールです。
デザインパーツを効率的に管理する「コンポーネント」機能や、様々な画面サイズに対応するレイアウトをシミュレーションできる「オートレイアウト」機能などが充実しています。
さらに、複数人で一つのデザインを同時に編集できるリアルタイムの共同編集機能や、エンジニアにデザインの寸法や色情報を正確に伝える共有機能が非常に強力です。
これらの特長から、チームで行うWEBサイトやアプリの設計・開発プロジェクトにおいて、全体のハブ(中心)として機能します。
Photoshop:写真補正やLP・バナー制作に最適
Photoshopは、その名の通り「写真・画像編集」を最も得意とするツールです。
FigmaのようなUIデザインツールでは難しい、写真の高度な合成や繊細な色調補正、人物の肌を綺麗に見せるレタッチといった専門的な画像加工を行えます。
そのため、1枚の絵としての完成度がプロジェクトの成果を大きく左右する、ランディングページ(LP)のメインビジュアルや、ユーザーの目を引く訴求力の高いバナー広告の制作において最適です。
WEBサイト全体の設計はFigmaで行い、そこで使用する高品質な画像パーツをPhotoshopで作り込んで配置する、といった使い分けが一般的です。
Illustrator:紙媒体やロゴ制作に最適
Illustratorは、どれだけ拡大・縮小しても画質が絶対に劣化しない「ベクターグラフィックス」という形式の画像を扱う専門ツールです。
この特性から、様々なサイズで使われるWEBサイトのロゴやアイコンパーツの作成に最も適しています。
また、WEBで標準のRGBカラーだけでなく、印刷で用いられるCMYKカラーにも対応している点が大きな特徴です。
このため、WEBサイトのデザインとあわせて、名刺やパンフレットといった紙媒体のデザインも手掛ける場合には必須のツールとなります。
WEBデザインツールを選ぶ際の注意点
WEBデザインツールを選ぶ際の注意点は、以下の六つです。
- 成果物に応じてツールを選ぶ
- ツールが無料・有料かどうかで選ぶ
- 「多機能=良いツール」というわけではない
- 自分のPC環境(Windows/Mac)で快適に動作するか確認する
- 日本語の情報やコミュニティが充実しているか確認する
- 一度契約すると他ツールへの乗り換えは大変
成果物に応じてツールを選ぶ
「何を作りたいのか」を明確にすることが最も重要です。
例えば、「アプリのUIデザイン:Figma」「アニメーションバナー:Google Web Designer」「イラスト中心のサイト:Krita, Illustrator」のような選定方法があります。
「みんなが使っているから」という理由ではなく、自分のキャリアプランや目指す制作物から逆算して考えましょう。
ツールが無料・有料かどうかで選ぶ
多くの高機能ツールは、月額または年額課金のサブスクリプション形式です。
初めのうちは、Figmaのように無料でも十分な機能が使えるツールから始めるのがおすすめです。
自分の学習フェーズや経済状況に合わせて判断しましょう。
「多機能=良いツール」というわけではない
Photoshopのように多機能なツールは、できることが多い反面、操作が複雑で学習に時間がかかる場合があります。
一方で、Balsamiqのように、機能が絞られているツールの方が、ワイヤーフレーム作成といった特定の目的においては効率的であると言えます。
自分の目的に不要な機能は、むしろ学習のノイズになり得ると考えましょう。
自分のPC環境(Windows/Mac)で快適に動作するか確認する
ツールによっては対応OSが限定される場合があります(例:SketchはMac専用)。
また、Figmaなどのブラウザーベースのツールでも、パソコンのメモリやCPUといったスペックによっては動作が重くなる可能性に注意が必要です。
契約前に必ず無料体験版などを利用し、自分のパソコンでストレスなく動くかを確認してください。
日本語の情報やコミュニティが充実しているか確認する
独学で学ぶ上で、日本語のチュートリアル記事や動画、質問できるコミュニティの存在は非常に重要です。
FigmaやAdobe製品は日本語情報が豊富ですが、海外製のマイナーなツールは英語情報しかなく、トラブル解決に苦労する可能性があります。
XやYouTubeなどで、そのツールの情報交換が活発かどうかも調べてみると良いでしょう。
一度契約すると他ツールへの乗り換えは大変
特定のツールでデザインデータを作り込んでしまうと、後から別のツールに完全に移行するのは手間とコストがかかります。
ファイル形式に互換性がなく、デザインを最初から作り直しになるケースも少なくないため、最初のツール選びは慎重に行いましょう。
現役デザイナーも実践するWEBデザインツールを使いこなすコツ
ツールは使えるだけでは不十分です。
プロとして効率的に、質の高いデザインを生み出すための4つのコツを紹介します。
- まずは好きなデザインを真似る
- ショートカットキーを覚えて作業スピードを上げる
- プラグインや拡張機能を活用してツールをカスタマイズする
- ツール操作だけでなくデザインの4大原則も意識する
まずは好きなデザインを真似る
最初は優れたデザインをそっくり真似る「模写」から始めることを推奨します。
Pinterestや「MUUUUU.ORG」などのギャラリーサイトで見つけたお手本デザインを、Figmaなどで再現してみましょう。
模写を通じて、レイアウトの組み方、余白の使い方など、優れたデザインの裏側にある「構造」や「意図」を体感的に学べます。
ショートカットキーを覚えて作業スピードを上げる
プロとアマチュアの差は、ツールの操作スピードに顕著に現れます。
マウスでメニューを探す時間をなくし、キーボード操作を主体にすることで、作業効率は格段に向上するでしょう。「長方形を作る(R)」「テキスト(T)」など、よく使う基本的なものから意識して少しずつ覚えるのがおすすめです。
プラグインや拡張機能を活用してツールをカスタマイズする
Figmaなどのツールには、機能を拡張する「プラグイン」が豊富に用意されています。
- ダミー画像を自動で挿入する
- 登録した配色を一括で適用する
- アイコンを検索して挿入する
上記のように、面倒な作業を自動化でき、自分の作業スタイルに合わせてツールを「自分仕様」にカスタマイズする楽しさと重要性を知っておきましょう。
ツール操作だけでなくデザインの4大原則も意識する
ツールを使いこなせても、デザインの基本原則を知らなければ「ただのオペレーター」になってしまうかもしれません。
デザインの質を上げるには、以下の4大原則を意識することが不可欠です。
- 近接:関連する要素を近づける
- 整列:要素を意識的に整列させる
- 反復:デザイン要素を繰り返し使う
- 対比:要素に強弱をつける
ツールはあくまで「手段」であり、目的は「情報を整理し、分かりやすく伝えること」であるという本質的な視点を忘れないようにしましょう。
WEBデザインツールに関するよくある質問
絵心やデザインセンスがなくても大丈夫?
全く問題ありません。
WEBデザインは、絵画のような芸術的センスよりも、情報を整理し、ユーザーの使いやすさを追求する「論理的思考力」の方が重要です。
センスは、デザインの原則を学び、良いデザインをたくさんインプットすることで後天的に磨かれます。
パソコンが苦手でも使いこなせるようになる?
問題なく使いこなせるようになります。
Figmaのような最近のツールは、直感的な操作で扱えるように設計されています。
また、YouTubeやブログに初心者向けの丁寧なチュートリアルが豊富にあるため、一つひとつ真似しながら進めれば、誰でも基本操作は習得可能です。
無料のツールだけでWEBデザイナーとして稼げる?
無料ツールだけで稼ぐことは可能ですが、限界もあります。
Figmaの無料プランは非常に優秀で、小規模な個人案件であれば十分に納品まで可能です。
しかし、企業で働く場合や大規模なプロジェクトでは、有料プランの機能(バージョン管理など)や、Photoshop、Illustratorとの連携が求められるケースがほとんど。
「まずは無料で実績を作り、稼げるようになったら有料プランに投資する」というステップをおすすめします。
最初に学ぶべきツールはどれ?
最初に学ぶべきツールに迷ったら、Figmaがおすすめです。
Figmaは、無料で利用でき、現在の業界標準である点から求人数が圧倒的に多いのが特徴です。
また、対応OSもWindows/Macの二つに対応しているため、多くのユーザーに支持されています。
1つのツールを習得するのに、どのくらいの学習時間が必要?
目指すレベルによりますが、以下の時間が目安です。
- 基本操作の習得:毎日1〜2時間の学習で2週間〜1ヶ月
- ツールの各機能が一通り使える状態
- 簡単なデザインを自力で作れる:100〜200時間
- 簡単なLPやバナーを模写・制作できる状態
- 実務レベル:300時間以上
- 応用機能を使いこなし、効率的にデザインを制作できる状態
ただし、ツールの進化は速いため、常に学び続ける姿勢が重要です。
まずは無料カウンセリングで不安を解消
この記事を読んで、学ぶべきツールや方法はわかったものの、「自分一人で本当にやりきれるだろうか」「自分のキャリアプランに合った、もっと具体的なアドバイスが欲しい」といった新たな不安を感じている人もいるかもしれません。
ツール選びや学習は、WEBデザイナーになるためのスタートラインに過ぎません。
最短でゴールにたどり着くためには、専門家に伴走してもらい、自分だけの最適なロードマップを手に入れることが最も確実な方法と言えるでしょう。
WEBCOACHの無料カウンセリングでは、Web業界のプロコンサルタントがあなたのキャリアの悩みを丁寧にヒアリングし、最適な道筋を提案します。
少しでも相談してみたいと感じたら、ぜひ一度、お気軽にお申し込みください。