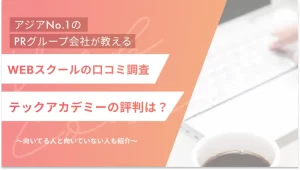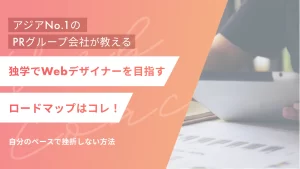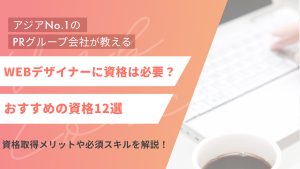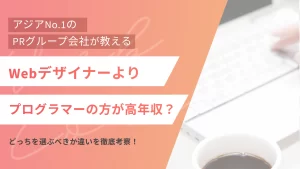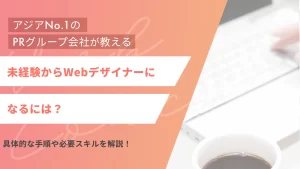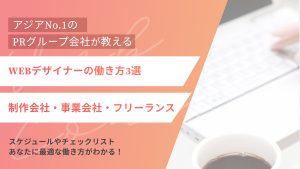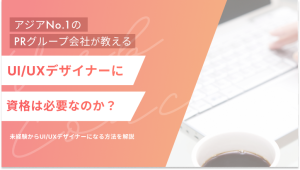【回答例付き】未経験WEBデザイナーの面接で聞かれる質問20選|キャリアプランや服装も解説
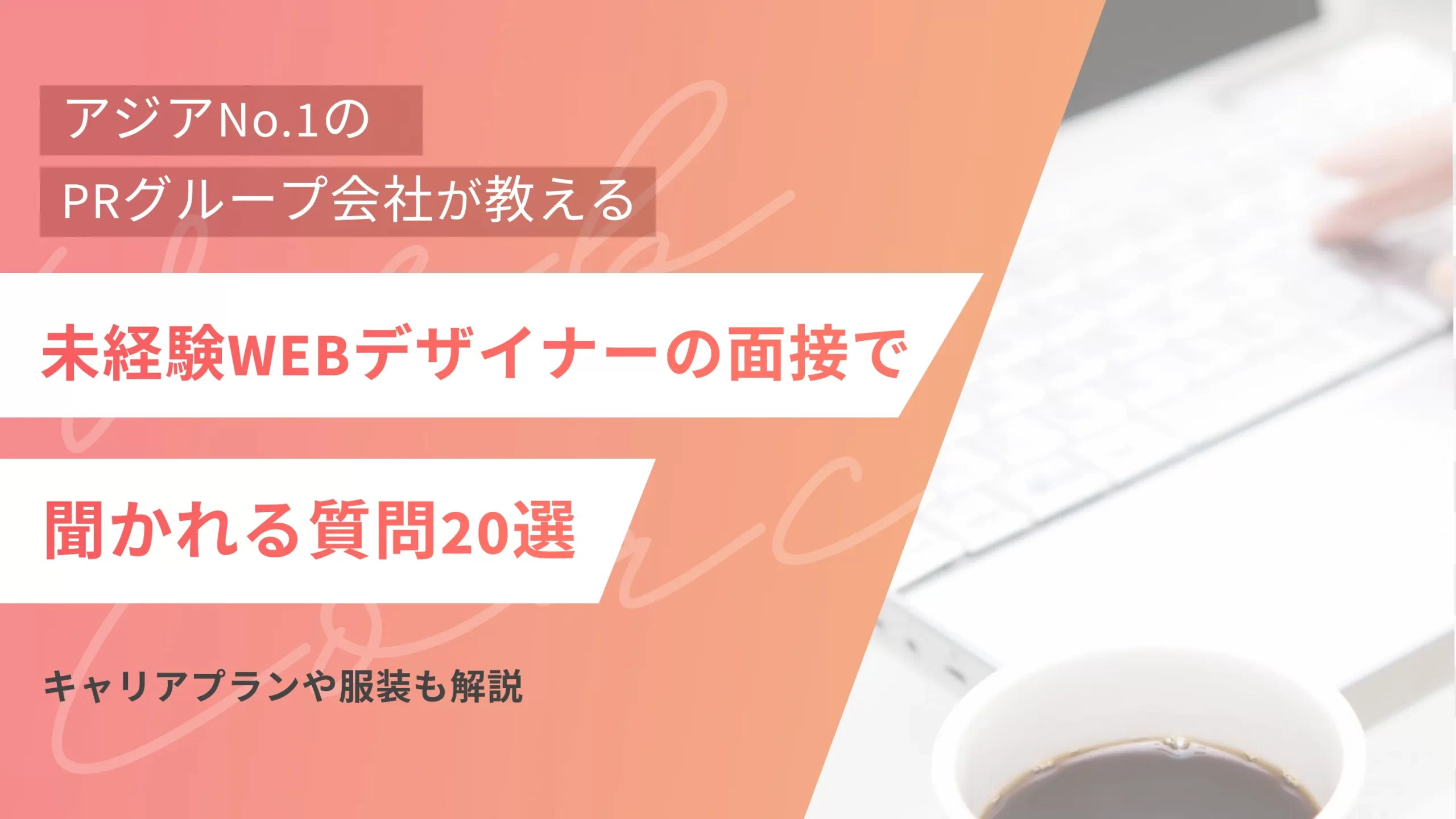
- WEBデザイナーの面接で何を聞かれるか不安
- 質問に対する回答例を知りたい
- 服装や髪色はどんなものがいいのか分からない
本記事ではこれらの悩みを、Webデザインスクールの「WEBCOACH」で授業をしている現役講師が解決します!
この記事を読めば、WEBデザイナーの面接で対策すべき内容が全て分かります!
- WEBデザイナーの面接で聞かれる質問と回答例
- キャリアプランの回答方法や考え方
- されて嫌な質問の答え方
- 未経験者が避けるべき怪しい求人
 WEBCOACH 編集部
WEBCOACH 編集部せっかく書類選考に通過しこぎつけた面接。
万全の対策をして、必ず採用されるようにしましょう!


監修 WEBCOACH 編集部
WEBCOAHは、WEBデザイナーやWEBマーケターなどさまざまなWEBに関する職業へのキャリアチェンジまでの全てを学び理想の”収入と働き方”、どちらも叶えるためのマンツーマンWEBスクールです。当メディアでは、WEBデザイナーやWEBマーケターに必要なスキルの身につけ方から、転職に関するノウハウ、ちょっとしたTipsまで幅広いコンテンツを発信しています。
【プロが監修】WEBデザイナーの面接でよく聞かれる質問20選!
WEBデザイナーの面接でよく聞かれる質問20個を、回答例とともに解説します。
質問は下記に分けて解説します。
経験問わず聞かれる質問
- これまでのキャリアを含め自己紹介をしてください
- 弊社の志望動機を教えてください
- 会社選びの軸は何ですか?
- 現職の退職理由を教えてください
- 他にどんな会社を受けていますか?
- 今後のキャリアプランについて教えてください
- マネジメント経験の有無について教えてください
- 希望年収をお聞かせください
- いつ頃から入社可能ですか?
これまでのキャリアを含め自己紹介をしてください
どのような職種であっても、この質問は必ず聞かれます。
面接官が応募者を純粋に理解する上で必要な質問です。
話し方や雰囲気から応募者の人柄を理解する目的もあるでしょう。
注意点として、履歴書や職務経歴書で記述していることを全て細かく説明すると、冗長かつ長い回答になる傾向です。そのため、ある程度まとめた内容で1分〜2分程度で回答することをおすすめします。
回答例
山田太郎と申します。
新卒から3年間、製造業の事務職として勤務しております。
主な業務は、営業担当者からの依頼に基づく見積書や請求書の作成、受発注データのシステム入力と管理、来客・電話応対です。
日々の業務では、複数の部署と連携しながら、円滑な業務遂行をサポートすることに努めておりました。
特に、請求書発行業務においては、膨大な件数の処理を正確かつ迅速に行い、締め日までの発行漏れゼロを継続しております。
また、新入社員のOJT担当として、業務フローの説明や進捗管理も行っておりました。
以上、本日はよろしくお願いいたします。
回答の解説
最初に現在の職種と勤務年数を簡潔に述べることで、面接官が応募者を素早く理解できます。
その後の業務内容の説明では、定量的な成果(発行漏れゼロなど)を交えつつ、複数の部署との連携やOJT担当といった役割を伝えることで、責任感や協調性、育成経験があることを示しています。
このように、これまでの業務内容を簡潔に、かつ具体的に説明することが有効です。
弊社の志望動機を教えてください
志望動機は、いくつかの理由に絞って回答すると良いでしょう。
必ず結論ファーストで回答してください。
なるべく、その理由に魅力を感じた背景などを実体験ベースで回答できると良いです。
採用企業としては、どこまで企業研究をしているかが把握でき、自社への熱量がわかるでしょう。
他社でも言えるような内容では信頼性に欠ける場合がありますが、複数個の理由が重なる場合は、貴社ならではの魅力として伝えられます。
回答例
私が貴社を志望する理由は2点あります。
貴社が小売店のホームページ制作実績を豊富にお持ちである点と、未経験者への研修制度が手厚く整っている点に魅力を感じたからです。
現職の小売店で販促物デザインを担当し、自身のデザインしたポップが直接売上向上に貢献する喜びを実感して以来、WEBデザインを通じて小売業界の活性化に貢献したいという思いが強くなりました。
貴社のWEBサイトで拝見した〇〇(具体的な小売店の制作事例)のホームページは、ユーザーの購買意欲を巧みに刺激するデザインであり、私の目指すWEBデザイナー像と合致しています。
また、WEBデザイナーとしてキャリアをスタートするに当たって、貴社のように未経験からでも実践的なスキルを習得できるよう、体系的な研修制度が用意されていることは非常に魅力的です。
これまでの販売員として培った、お客さまのニーズを汲み取るヒアリング力や、店舗運営で得た小売業界への理解を活かし、一日も早く貴社のWEBデザイナーとして貢献したいと考えております。
回答例の解説
最初にホームページ制作実績と研修制度に惹かれているという結論を持っていき、その後に結論を理由づける現職での経験を出すことで説得力が増しています。
このように、実体験と紐づけたり、その企業を見つけたきっかけ等があると熱量や企業研究をしっかりしていると判断されやすいです。
会社選びの軸は何ですか?
志望動機に合わせて聞かれるのが会社選びの軸です。
優先する物事について回答できると良いでしょう。
例えば、研修制度が整っている環境かどうかや、自社サービスを持っているかどうか、所在地、福利厚生の充実度などがあります。
大切なのは、志望動機とずれがないことです。
回答例
私の会社選びの軸は、下記です。
- デザイン制作の代理店であること
- 未経験者向けの研修制度が整っていること
- 東京都で働けること
まず、これから多くのデザイン制作に触れ多方面への経験を積みたいので、インハウスデザイナーではなく代理店のデザイナーとして働ける環境を求めています。
また、現在デザインの実務経験がないため、研修制度が整っていて現場に出る前にある程度学べる環境があると嬉しく存じます。
今後、WEBデザイナーとしてのキャリアを発展させていくためにも、東京都で働きたいと考えています。
回答例の解説
最初に会社選びの軸を明確に提示することで、面接官が応募者の優先順位を素早く理解できます。
それぞれの軸について、なぜそれが重要なのかを簡潔に説明し、志望動機で述べた内容(未経験、代理店希望など)との一貫性を持たせている点も有効です。
現職の退職理由を教えてください
応募者がどのようなタイミングや背景で退職を決める考えがあるのか、どんな環境にストレスを感じるのかを確かめる意図があります。
一人採用するに当たる費用は採用費と呼ばれ、場合によっては数百万円かかるケースもあります。
そのため、採用担当としては早期退職するような人は採用できません。
応募者がストレスを感じる内容が自社にないか確認する目的が強いでしょう。
基本的に以前の会社の悪口を言うのはNGです。
なるべくポジティブな理由に変えましょう。
また、体調を崩してしまったなど病歴も評価されづらい傾向です。
嘘をつくのはいけませんが、ネガティブな理由は控えてください。
回答例
現職の退職を検討した理由は、WEBデザイナーとして専門性を深め、キャリアを築きたいという強い思いが芽生えたためです。
新卒で入社した際、私自身の自己分析が不十分で、将来のキャリアパスを明確に描けていませんでした。
しかし、小売店での販促物デザインを担当する中で、デザインの力で顧客の行動を促し、売上という具体的な成果に貢献できるWEBデザイナーという仕事に大きな魅力を感じるようになりました。
現職の販売員という立場では、WEBデザインの業務に携わる機会がなく、この分野でスキルを習得し、実践していくことが難しいと判断いたしました。
そのため、WEBデザイナーとして本気でキャリアチェンジを目指すには、新たな環境に身を置く必要があると考え、退職を決意いたしました。
回答例の解説
退職理由を「WEBデザイナーとして専門性を深めたい」という前向きな目標に焦点を当てています。
新卒時の自己分析不足を認めつつも、現職での経験からWEBデザインへの興味が明確になった過程を具体的に説明することで、責任感と成長意欲をアピールしています。
ネガティブな不満ではなく、未来志向で自身のキャリアアップに繋がる退職であることを伝えている点が評価につながるでしょう。
他にどんな会社を受けていますか?
他にどんな会社の選考を進めているのか確認されることも多々あります。
これには、応募者の選考基準の一貫性や企業研究の深さを確認する意図があるでしょう。
例えば、志望動機や会社選びの軸で、デザインの代理店で働きたいと伝えながらも、他に受けている会社がインハウス系だと辻褄が合わず信頼性が欠如します。
回答例
現在、貴社を含めて〇〇社と〇〇社が面談予定です。
その他〇〇件の書類応募をしており、返信待ちといったステータスです。
回答例の解説
選考中の企業を具体的に挙げつつ、応募状況を正直に伝えています。
面接を受けている企業(貴社)を含めることで、隠し事なく話している姿勢を示しています。
多数応募していることは自然なことであるため、選考段階にある企業の数を正直に伝えることで、選考状況の全体像が面接官に伝わりやすくなります。
今後のキャリアプランについて教えてください
WEBデザイナーになった後にどんなキャリアを想定しているのかという質問です。
WEBデザイナーになることが目的になっていないか、求めているキャリアが自社で実現できることなのかなどを確認したい意図があります。
仮にWEBデザイナーとして3年ほど経験を積んだのち、フロントエンジニアになり、WEBディレクターになりたいとなれば、フロントエンドの案件がない会社にとってはネガティブに映る可能性もあります。
回答例
今後のキャリアプランについては、まず入社後3年ほどで、WEBデザイナーとしてUI/UXデザインの専門性を深め、ユーザー体験を最大化できるスキルを習得したいと考えております。
特に貴社が手掛けられている〇〇(具体的な制作事例やサービス)のような、ユーザーが直感的に「使いやすい」と感じるサイト設計に深く携わりたいです。
長期的には、将来的にはWEBデザインのスペシャリストとして、お客さまの課題に対し、デザインを通して最適なソリューションを提供できる存在になりたいと考えております。
常に新しいデザインのトレンドや技術を学び続け、貴社のWEBデザインの品質向上に貢献できる人材を目指します。
貴社であれば、多様なプロジェクトを通して、この専門性を高めていけると確信しております。
回答例の解説
まず短期的な目標(入社後3年ほど)としてUI/UXデザインの専門性向上を明確に示し、具体的な貴社の制作事例に触れることで、企業への理解度と入社後の貢献意欲を伝えています。
長期的なビジョンとして「WEBデザインのスペシャリスト」を目指すことを語り、常に学習を続ける姿勢を示すことで、入社後の成長意欲と定着への意欲をアピールできるでしょう。
マネジメント経験の有無について教えてください
リーダーやマネージャーポジション、その候補として面接を受ける場合に重要な評価ポイントとなります。
平均年齢が若い企業などでは、若手をマネジメントできる人材は非常に貴重な人材でしょう。
プロジェクトの進行管理やタスク振りなどのディレクション経験と、1on1など一人ひとりのメンタル面でのマネジメント経験、両方の回答ができると良いです。
OJT経験などがあれば、それも評価に良い影響を及ぼすでしょう。
これらは別業界での経験でも評価されるため、WEBデザインのプロジェクトや会社での経験でなくとも積極的にアピールしてください。
回答例
はい、直接的な「マネージャー」という役職ではありませんが、現職の事務職において、新人スタッフのOJT担当や、特定業務のプロジェクト進行管理を経験してまいりました。
例えば、新しいデータ管理システムの導入プロジェクトでは、私が中心となってシステムベンダーとの連携窓口となり、社内メンバーへのタスクの振り分けや、進捗状況の管理を行いました。
約3ヶ月のプロジェクト期間中、メンバー間の認識齟齬がないよう週次で進捗共有会を実施し、計画通りにシステムを稼働させることができました。
また、新入社員が入社した際には、業務フローの説明から日々の疑問点への対応まで、寄り添ったサポートを心がけておりました。
これらの経験を通して、相手の状況を理解し、円滑に業務を進めるためのコミュニケーション力や、目標達成に向けて全体を俯瞰する視点を養ってまいりました。
回答の解説
「マネージャー」という直接的な役職がなくても、OJT担当やプロジェクト進行管理といった具体的な経験を挙げることで、リーダーシップや育成能力があることを示しています。
データ管理システムの導入プロジェクトでの具体的な役割や成果、そして新入社員の育成におけるサポート内容を詳細に説明することで、責任感とコミュニケーション能力をアピールし、それが貴社でどう活かせるかを示している点が評価につながるでしょう。
希望年収をお聞かせください
企業側の出せる年収で入社してくれる可能性がどれくらいあるのかを測る質問です。
大前提として、募集要項に年収の上限下限が決められているはずです。
そこを大幅に超えるような金額は避けてください。
また、自己評価が適正なのかも測られています。
どんなスキルや経験があるからこれくらいを希望しているという根拠を伝えられると良いでしょう。
「現在これくらいもらっているので、これくらいが良いです」というだけでは、場合によってはネガティブに取られる可能性もあります。
その年収が世間の評価とずれている場合は自己評価が不適切だと見られることもあるでしょう。
回答例
私の希望としましては、年収〇〇万円を希望いたします。
これは、現職でいただいている年収と同水準であります。
未経験からのWEBデザイナーへの転職ではありますが、前職の小売店での販売経験で培った「顧客の潜在ニーズを汲み取るヒアリング力」や、「売上向上に直結する販促物を作成した経験」は、WEBデザイナーとしてお客さまのビジネス課題を解決していく上で活かせると考えております。
これらのスキルや、入社後にWEBデザインを通して貴社へ貢献していきたいという思いで希望させていただきました。
回答の解説
まず具体的な希望年収を提示し、それが現職と同水準であると説明することで、現実的な希望であることを伝えています。
その上で、未経験ながらも前職で培ったヒアリング力や販促物制作の経験といったポータブルスキルが、WEBデザイナーとして貴社に貢献できる根拠であると明確に示しています。
これは、自己評価が単なる希望ではなく、具体的な経験に裏打ちされていることをアピールする有効な方法です。
いつ頃から入社可能ですか?
面接を受けているからといって、来月から入社させてくださいという人はほぼいません。
現在無職でない限りはありえないでしょう。
採用担当としては、いつ頃から可能かによっても採用可否を決める理由になり得ます。
月ごとの予算や目標件数などがあるためです。
基本的には内定後2ヶ月後が最適です。
それであれば、現職の引き継ぎも有給消化、次の会社での事務処理なども間に合うでしょう。
半年後などを希望する場合は、相手を納得させるだけの回答が必要です。
回答例
内定を頂けましたら、現職の引き継ぎ期間を考慮し、約2ヶ月後の〇月上旬頃からの入社が可能でございます。
現在の業務を円滑に引き継ぎ、貴社にご迷惑をおかけしない形で入社したいと考えております。
もし貴社にご希望の入社時期がございましたら、調整できるよう努めますので、お気軽にお申し付けください。
回答例の解説
内定後の具体的な入社可能時期(約2ヶ月後)を明確に伝えています。
現職の引き継ぎ期間を考慮していることを伝えることで、責任感があるという印象を与えられるでしょう。
また、貴社の希望する入社時期に柔軟に対応する姿勢を見せることで、入社への意欲と協調性をアピールできています。
経験者によく聞かれる質問
- 思い入れのあるプロジェクトについてお聞かせください
- そのプロジェクトに成果について具体的にお聞かせください
- 得意領域や得意な業務内容について教えてください
- WEBデザイン以外のWEBスキルについて教えてください
- 使用可能なツールについてお聞かせください
思い入れのあるプロジェクトについてお聞かせください
これまでの成果や制作物に関する質問と等しいです。
経験者の場合は応募時にポートフォリオも提示していると思うので、その内容の中で特に思い入れがあるものや実績を上げられたものを伝えられると良いでしょう。
その際は、どういった理由で思い入れがあり、どんな体制で作成し、どんな工夫や体制で進めたのかをセットで回答してください。
回答例
はい、私が最も思い入れのあるプロジェクトは、前職で担当した〇〇株式会社様のECサイトリニューアル案件です。
このプロジェクトは、既存ECサイトのユーザビリティの低さによる購入率の伸び悩みが課題でした。
私が担当したのは、ユーザー導線の設計から商品ページのUI改善、そして最終的なデザイン実装までの部分です。
プロジェクトを進める中で、特に力を入れたのは、詳細なユーザーヒアリングと競合サイトの分析に基づいた情報設計の見直しです。
例えば、商品カテゴリの分類方法を根本から変更したり、購入ボタンまでのステップを簡略化したりといった改善提案を積極的に行いました。
チーム内では、私を含めデザイナー2名、エンジニア3名、ディレクター1名の体制で、週に2回の定例ミーティングで進捗を共有し、密に連携を取りながら進めました。
回答例の解説
まず、プロジェクトの具体的な概要と自身の担当範囲を明確に伝えています。
課題(購入率の伸び悩み)と、それに対する自身のアプローチ(ユーザーヒアリング、情報設計の見直し、具体例)を詳細に説明することで、デザイン思考と問題解決能力をアピールできています。
チーム体制や連携方法にも触れることで、協調性やプロジェクト遂行能力も示しているでしょう。
そのプロジェクトに成果について具体的にお聞かせください
デザインは目的があって行うものなので、具体的な成果としてどんな数字が改善されたのかなどを求められます。
具体的な成果があると非常に評価されるポイントとなるでしょう。
回答例
特に印象的だったのは、ユーザーテストで初期プロトタイプが思ったような反応を得られなかった際、チームで徹底的に原因を分析し、ユーザー視点に立ち返って改善を繰り返したことです。
結果として、リニューアル後のECサイトは、購入率が前年比で1.5倍に向上し、お客さまからも直接感謝の言葉をいただきました。
この経験を通じて、WEBデザインは単に見た目を美しくするだけでなく、「ユーザーの行動を促し、ビジネスの成果に直結させるための課題解決ツールである」ということを強く実感しました。
このプロジェクトで培った、成果へのコミット力と、チームで課題を乗り越える経験は、貴社でも必ず活かせると考えております。
回答例の解説
前の質問で述べたプロジェクトの具体的な成果を、「購入率が前年比で1.5倍向上」という定量的な数字で示し、客観的な事実として説得力を持たせています。
困難をチームで乗り越えた経験と、そこから得られた学び(デザインのビジネスへの貢献)を語ることで、単なるスキルだけでなく、仕事への深い理解と責任感をアピールしているでしょう。
得意領域や得意な業務内容について教えてください
WEBデザインといえど、作るものや業界など数多くのパターンがあります。
自分がどんな業界のどんな制作物に強みを持っているのか、具体的な根拠を持って説明できると良いでしょう。
また、その内容が応募企業で活かせるとさらに良いです。
回答例
不動産業界のWEBサイトやLP(ランディングページ)のデザインが得意です。
前職では、不動産会社のプロジェクトを約3年間担当しておりました。
そのため、ターゲット層の購買心理や、物件情報を効果的に伝えるためのレイアウト、問い合わせに繋がりやすい導線設計など、不動産WEBサイトならではのユーザー行動や業界特有の知見が豊富にあると自負しております。
具体的には、複雑な物件情報をいかに分かりやすく整理し、ユーザーにストレスなく閲覧してもらうかという情報設計やUI/UX設計において、特に強みを発揮できると考えております。
貴社でも不動産系の案件がございましたら、これまでの経験と知見を活かし、即戦力として、より早く貢献できると考えております。
回答例の解説
得意領域を「不動産業界のWEBサイトやLPデザイン」と具体的に限定し、その理由として「3年間の担当経験」と「業界特有の知見」を明確に述べています。
情報設計やUI/UX設計といった具体的なスキルを挙げつつ、それが「不動産WEBサイトならではのユーザー行動」にどう活かされるかを説明することで、専門性と実務への適応力をアピールしています。
応募企業で活かせる可能性に言及している点も有効です。
WEBデザイン以外のWEBスキルについて教えてください
WEBマーケティングや動画編集など、他のWEBスキルがあるかを確認する質問です。
もちろん、ないからといってネガティブに取られることはありませんが、あると非常に評価されます。
例えば、広告運用の経験もあり、CPA(顧客獲得単価)を下げた経験などもあれば、企業からすればデザイナーとマーケターを採用できたものと捉えられ、非常に高評価につながるでしょう。
回答例
現時点では、WEBデザインに特化して学習を進めてきたため、WEBマーケティングの専門知識や動画編集スキルといった、WEBデザイン以外のWEBスキルは持ち合わせておりません。
しかし、WEBデザイナーとしてお客さまのビジネスに貢献するためには、WEBサイトの制作だけでなく、その先の集客や成果につなげるマーケティングの視点も非常に重要であると認識しております。
そのため、今後は実務経験を積む中で、SEOに関する知識も積極的に学び、デザインとマーケティングの両面からWEBサイトの価値を高められる人材になりたいと考えております。
回答例の解説
現時点ではWEBデザイン以外の専門スキルはないと正直に伝えています。
しかし、そこで終わらず、WEBマーケティングやSEOといった関連分野の重要性を認識しており、今後学ぶ意欲があることを具体的に示しています。
これは、WEB業界全体への関心の高さと、将来的なスキルアップへの前向きな姿勢をアピールする有効な方法です。
使用可能なツールについてお聞かせください
WEBデザインツールは多種多様です。
大抵はAdobe製品が多いですが、中には古いツールを使ってデザインしている人もいるでしょう。
基本的にはブラウザでの共同編集などが求められるため、会社内で同じツールを使うことが多いです。
そのため、会社で使われているツールが使えるかといった確認目的があります。
回答例
現在、WEBデザインの実務ではFigma、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、そしてAdobe XDを使用しております。
また、実務経験はありませんが、SketchやCanvaなども個人的な学習や趣味の範囲で触れております。
貴社で使用されているツールに合わせて、必要であれば新たなツールの習得にも意欲的に取り組んでまいります。
回答例の解説
実務で使える主要なWEBデザインツールを具体的に羅列し、それぞれの熟練度(実務で使用、趣味で利用など)を明確に分けて伝えています。
未経験者によく聞かれる質問
- どうしてWEBデザイナーを目指そうと思ったのですか?
- WEBデザインの学習はされていますか?
- WEBデザインの学習方法について教えてください
- 大きな修正依頼が発生した際はどのように対応しますか?
- コーディングスキルについてお聞かせください
- (ポートフォリオを見ながら)このデザインの意図を教えてください
どうしてWEBデザイナーを目指そうと思ったのですか?
未経験者の場合、この質問は必ず聞かれます。
なぜWEBデザイナーでなければならないのかを、実体験やこれまでの努力と結びつけてしっかり伝えましょう。
熱意とそれに伴った行動が大切です。
安易にリモートワークができるとか、フリーランスになりやすいといった理由は避けてください。
サボりたいとか早期退職などと疑われる可能性があります。
回答例
現職の小売店で販売員として働く中で、店舗の販促物としてポップやポスターのデザインを担当する機会がありました。
最初は手探りでしたが、私がデザインしたポップを見てお客さまが商品を手に取り、実際に売上が向上した時に、言葉ではなく視覚で伝えるデザインの大きな力と、その影響力に大変な喜びを感じました。
この経験から、より専門的にデザインの力を追求し、WEBサイトという形で多くの人や企業の課題解決に貢献できるWEBデザイナーという仕事に強く惹かれるようになりました。
単に美しいものを作るだけでなく、ユーザーの行動や感情に働きかけ、ビジネスの成果につなげるデザインができることに、計り知れない魅力を感じています。
現在は、WEBデザインスクールで専門知識やツールの使い方を学び、ポートフォリオ制作にも意欲的に取り組んでおります。
これまでの経験で培ったお客さまのニーズを汲み取る力を活かし、WEBデザイナーとして貴社に貢献したいと考えています。
回答例の解説
現職での具体的な成功体験(ポップ制作で売上貢献)をWEBデザインへの興味に繋げ、その喜びがWEBデザイナーを目指すきっかけになったことを明確に伝えています。
WEBデザイナーの仕事の本質である「課題解決」「ビジネス貢献」への魅力を語り、単なる憧れではないことを示しているでしょう。
WEBデザインスクールでの学習状況にも触れることで、熱意と行動が伴っていることをアピールできています。
WEBデザインの学習はされていますか?
現在完全未経験なのか、実務経験がないだけで知識自体はあるのかを確認しています。
独学にしろ、スクールにしろしっかり伝えて、熱意だけでなく行動も伴っていることを伝えましょう。
基本的に、完全未経験で何も勉強していないとなると、採用は難しい傾向です。
どのような学習を、どれくらいしているのか伝えてください。
素直にしているのか、していないのかを回答するのが良いです。
回答例
はい、WEBデザイナーを目指すに当たって、現在独学で学習を進めております。
デザインの4原則や色彩効果、タイポグラフィなどの基礎知識はもちろん、Figmaの操作に関して学んでいます。
回答例の解説
学習状況を「独学で進めている」と明確に伝えています。
その上で、「デザインの4原則や色彩効果、タイポグラフィ」といったデザインの基礎理論と、「Figmaの操作」という具体的なツール名も挙げることで、どのようなスキルを学んでいるのかを具体的に示しています。
これにより、熱意だけでなく、実際に行動していることを効果的にアピールできています。
WEBデザインの学習方法について教えてください
未経験でWEBデザイナーを目指す場合、どのように学習を進めてきたのかは必ず聞かれる質問の一つです。
もしスクールに通っていた場合は、スクール名や学んだ内容を具体的に伝えましょう。
例えば、HTMLやCSS、Photoshopなどのツールの使い方を学んだ、ポートフォリオ制作の実践を行ったなど、学習内容を詳細に説明することがポイントです。
また、独学の場合も、参考にした教材やオンライン講座、制作した作品について具体的に触れることで、努力や熱意をアピールできます。
回答例
私は〇〇(スクール名)というWEBデザインスクールに通い、WEBデザイナーになるためのスキルを体系的に学びました。
具体的には、色彩心理やレイアウト構成といったデザインの基礎理論から、FigmaやAdobe Photoshop、Illustratorといった主要なデザインツールの操作方法まで、実務を想定したカリキュラムで習得しました。
また、WEBサイトの構造を理解するために、HTMLやCSSの基礎コーディングも学びました。
スクールでは特に、ポートフォリオ制作に力を入れ、実際にお客さまワークを想定した架空のWEBサイトやLP(ランディングページ)、バナーなどを複数制作しました。
講師の方々からは個別のフィードバックを頂くことで、ユーザー視点でのデザイン思考や、論理的なデザインプロセスを徹底的に叩き込んでもらいました。
回答例の解説
スクール名と、そこで学んだ内容(デザイン基礎、ツール操作、コーディング基礎)を体系的に説明しています。
特に「実務を想定したカリキュラム」「ポートフォリオ制作」「講師からの個別フィードバック」といった、実践的な学習と成長に繋がる要素を具体的に挙げることで、学習の質と自身の努力をアピールしています。
大きな修正依頼が発生した際はどのように対応しますか?
WEBデザインには修正がつきものです。
特に大きな修正が発生した場合に、どのように対応するかは重要なポイントとして面接で問われることがあります。
未経験者の場合、技術的な対応力よりも社会人としての対応力が重視されます。
この質問の背景には、報告・連絡・相談(報連相)のスキルや適切な報告ができるかどうかを見極める意図があります。
回答の際は、修正が発生したときに迅速に上司やチームに報告し、原因を確認して解決策を提案する姿勢を示すと良いでしょう。
回答例
大きな修正依頼が発生した際は、まず迅速に状況を把握し、上司やチームリーダーに報告・相談いたします。
修正内容と背景の確認、影響範囲と原因の特定、解決策の検討と提案について簡潔にまとめ報告します。
回答例の解説
「迅速な報告・相談」を冒頭に置くことで、報連相を重視する姿勢を示しています。
さらに、修正内容の正確な把握、影響範囲の特定、そして自分なりの解決策を検討・提案するという一連のプロセスを簡潔に述べることで、問題解決への主体性と、チームとして動く意識があることをアピールできています。
コーディングスキルについてお聞かせください
WEBデザイナーといえど、コーディングスキルがどれくらいあるのかは採用担当にとって大切な情報です。
コーディングに関しては、どの程度のスキルがあるのか、具体的に説明できるように準備しましょう。
例えば、HTMLやCSSの基礎的な知識を持っているのか、JavaScriptやCMSを使った実務経験があるのか、といったレベル感を明確に伝えることが重要です。
回答例
はい、コーディングスキルについては、HTMLとCSSは基礎的な記述であれば問題なく対応できます。
WEBサイトの構造を理解し、デザインカンプを基に正確にマークアップしたり、CSSでレイアウトや装飾を実装したりすることは可能です。
一方で、JavaScriptに関しては、現時点では記述することはできません。
しかし、JavaScriptがどのような役割を持ち、どのような動きや機能をWEBサイトに実装できるかについては、学習を通して理解しております。
そのため、エンジニアの人たちと「このデザインには〇〇の機能が必要なので、JavaScriptでこういった実装をお願いしたいです」といった具体的な会話や連携はスムーズにできると考えております。
回答例の解説
HTMLとCSSは基礎レベルで対応可能であることを明確に伝え、具体的に何ができるのか(マークアップ、装飾実装)を説明しています。
JavaScriptについては現時点では記述できないことを正直に認めつつも、その機能や役割は理解していることを示し、エンジニアとの円滑なコミュニケーションが可能である点をアピールしています。
これは、現状のスキルと、連携能力、そして今後の学習意欲をバランス良く伝える良い例と言えるでしょう。
(ポートフォリオを見ながら)このデザインの意図を教えてください
面接では、ポートフォリオを見ながらその作品について詳細を尋ねられることがよくあります。
特に、各作品のデザイン理由や制作過程で考慮した点、目的に応じた工夫などについて説明を求められることが多いです。
ポートフォリオに掲載している作品については、どのような思いで制作したのか、なぜそのデザインを選んだのか、具体的な回答を事前に準備しておきましょう。
回答例
こちらはオンライン英会話サービスの無料体験レッスンを訴求するバナーです。
ターゲットは「気軽に英会話を始めたい」と考えている社会人(20代〜30代)で、目的は無料体験へのクリック率向上でした。
このデザインで最もこだわった意図は、「一目でメリットが分かり、行動を促すシンプルさと視認性」です。
具体的には、サービスの特徴である「スキマ時間で学べる」というメリットを瞬時に伝えるため、イラストでパソコンとスマートフォンを並べ、どこでも学習できることを視覚的に表現しました。
メインカラーには、明るくポジティブな印象を与える水色と黄色を使用し、英会話へのハードルが低いと感じさせるように工夫しています。
文字情報が多いバナーにならないよう、キャッチコピーは「英語、始めよう!」と短く力強くし、視認性の高いゴシック体を選びました。
また、最もクリックしてほしいCTA(Call to Action)ボタンは、目立つ色(オレンジ)と、指差しアイコンを組み合わせることで、ユーザーの視線を強く誘導するよう意図しました。
回答例の解説
まず、作品の概要(オンライン英会話バナー)、ターゲット、目的を明確に示しています。
最もこだわった点として「シンプルさと視認性」というデザイン意図を挙げ、それを実現するために色、イラスト、フォント、CTAボタンといった具体的な要素をどのように選択し、工夫したかを論理的に説明しています。
これにより、単に見た目を語るだけでなく、ユーザーの行動を促すためのデザイン思考を持っていることを効果的にアピールできています。
【面接対策】よく聞かれるWEBデザイナーのキャリアプランについて
面接対策として、キャリアプランについての質問に備えることは重要です。
WEBデザイナーの面接でも、「将来的にどのようなキャリアを築きたいか」といった質問が一般的です。
未経験者の場合、具体的なキャリアプランを描くのが難しいこともありますが、少なくとも方向性は示せるように準備しておきましょう。
また、応募先企業の事業内容や役割に即したプランを示すことで、より説得力のある回答になります。
曖昧な答えを避け、具体的な目標を持つことが大切です。
WEBデザイナーのキャリアプラン例
WEBデザインのスペシャリストとして活躍する
仕事には主にプレイヤーとマネージャーの2つの役割があります。
Webデザインにおいても、プレイヤーとしてスキルを磨き続け、スペシャリストとして活躍するキャリアを選ぶ人も多いです。
この道を選ぶと、チームを動かす経験は得られませんが、自分の成果を直接感じることができるため、大きなやりがいを得やすいでしょう。
また、スキルアップに伴い、成長実感も強く感じられる点が特徴です。
一方で、会社員として働く場合、マネージャーの方が給与が高い傾向があるため、スペシャリストとしてのキャリアを追求する場合は、最終的に独立を目指すのが現実的です。
独立することで、自分のスキルを活かしながら、より自由な働き方や収入アップの可能性を広げられます。
スペシャリストとして活躍するためには、技術力の継続的な向上と、独立を視野に入れた計画が求められます。
WEBデザイン部署の統括をしたい
スペシャリストとしてのキャリアと異なり、マネージャーとしてWEBデザイン部署を統括することを目指すキャリアもあります。
大きな制作会社では、多くのWEBデザイナーを束ねるディレクターのさらに上に、統括部長やマネージャーが存在します。
このポジションでは、基本的に自分でデザインを行うことはなく、場合によってはディレクション業務すら担当しません。
主な役割は、採用や育成、組織の運営、他部署との連携など、会社全体の利益に直結する業務を担います。
そのため、社内での会議や調整業務が増えることが特徴です。
特に、チーム全体を効率的に運営し、目標達成をサポートするリーダーシップが求められます。
デザインスキルだけでなく、組織運営の視点やコミュニケーション能力を磨くことが、このキャリアパスで成功するための鍵となります。
いくつかの企業の社外CDOを兼任したい
CDOとは「チーフデザインオフィサー(Chief Design Officer)」の略で、企業のデザイン最高責任者を指します。
この役職では、単にデザイン部署を統括するだけでなく、企業全体のブランディング戦略や、組織内でのデザイン文化の醸成など、経営レベルの課題にも関与します。
特に企業規模が大きい場合、その役割は戦略的なものとなります。
こういった役職は、必ずしも社内に常設されるとは限らず、社外役員として外部の専門家が務めることも一般的です。
そのため、複数の企業で社外CDOを兼任するキャリアパスが存在します。
このような形でのキャリアは、これまでのスペシャリストやマネージャーといった道とは異なり、デザインを超えて経営視点が求められる点が特徴です。
このキャリアを目指すには、デザインスキルだけでなく、経営戦略や組織マネジメントの知識を磨き、幅広い視野を持つことが重要です。
他にもWEBスキルを身につける
WEBデザインだけでなく、広告運用、SEO、SNSマーケティングなど幅広いスキルを身につけ、WEB分野のジェネラリストとして活躍するキャリアパスもあります。
これは日本における一般的なジェネラリストの定義とは少し異なり、デザインだけでなくマーケティングや運用においても実績を出せる、いわば「WEBのプロフェッショナル」としての役割を指します。
このようなスキルセットを持つ人材は、フルスタックエンジニアに似た存在であり、「この人1人いれば何でも対応できる」と企業から高く評価されるでしょう。
幅広い業務に対応できる能力は、市場価値を大きく高めるポイントです。
このキャリアを目指すには、各分野の基礎を学びつつ、実践的な経験を積むことが重要です。
多様なスキルを活かしてWEB業界での存在感を高めたい人にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
キャリアプランの考え方
キャリアを考える際には、いくつかの一般的な手順を踏むと整理しやすくなります。
また、WEBデザイナーとしてのキャリアの全体像が見えていると、キャリアについて考えやすくなります。
WEBCOACHでは10,000人以上のデータに基づいたWEBデザイナーロードマップを配布中なので、ぜひ活用してください。
自分の現在地を理解する
キャリアを考える第一歩は、自分の現在地を正確に理解することです。
今の自分が何をできるのか、どこに強みや楽しさを感じるのかを振り返ることで、自然と合理的な方向性が見えてきます。
WEBデザイナーになりたての場合、経験不足から迷いが生じることもありますが、必ずしもWEBデザインの経験だけにこだわる必要はありません。
例えば、前職で教育担当として指導を楽しんでいた経験がある場合、それをキャリアのヒントにすることも可能です。
また、自分の苦手な分野を理解しておくことも重要です。
強みや興味、苦手な部分を明確にすることで、将来のキャリアを具体的に描きやすくなります。
このプロセスが、長期的な成功への土台を築く鍵となるでしょう。
理想の将来像を考える
キャリアプランを描く際、自分が将来どのような人物になりたいかを考えることが重要です。
それはWEBデザイナーとしての姿だけでなく、人としての生き方でも構いません。
例えば、「WEBデザイナーとしてマネージャーになり、新卒の教育に携わりたい」「年収1,000万円を達成しながら、家族との時間を大切にしたい」といった具体的な目標が挙げられます。
理想の将来像を持つことは、日々の努力の方向性を明確にする助けとなります。
目標は個人の価値観やライフスタイルに応じて異なりますが、自分にとっての「理想」をしっかり見据えることで、充実したキャリアを築くための土台ができます。
現在地と将来像のギャップを埋めていく
理想の将来像を実現するためには、現在の自分とのギャップを埋めていくことが重要です。
このプロセスを通じて、自分が進むべき道が明確になります。
例えば、WEBデザインのマネージャーになり組織の育成に携わりたい場合、デザインやディレクションの経験に加え、マネジメントスキルの習得が必要です。
一通りのスキルを習得した後は、積極的にマネージャー登用を行う企業へ移ることで、キャリアアップを図るのも効果的です。
一方で、年収1,000万円を達成しつつ家族との時間を大切にしたい場合、残業を避けながら高収入を得る方法を考える必要があります。
この場合、フリーランスとしての活動を視野に入れる方が現実的です。
特に、大きな案件を安定して受注するためには、スペシャリストとしてのスキルを極めることが欠かせません。
理想像に応じた具体的な行動計画を立てることで、着実にギャップを埋め、目標に近づける道筋が見えてくるでしょう。
未経験WEBデザイナーの面接に関するよくある疑問
服装・髪色について
服装については、スーツが最も無難で安心です。
WEBデザイナーの面接は比較的自由な印象を与える場合もありますが、スーツを選んで問題視されることはありません。
カジュアルな装いが許される場合でも、無地のTシャツにジャケットを合わせるなど、きちんと感を意識することが重要です。
不安がある場合は、迷わずスーツを選びましょう。
髪色については、自由であっても暗めが基本です。
明るい髪色はダークブラウン程度にとどめるのが良いでしょう。
どうしても明るくしたい場合は、入社後に職場の雰囲気を確認して徐々に変えることをおすすめします。
清潔感を重視した服装と髪色が、面接官に良い印象を与えるポイントです。
逆質問について
面接では、逆質問を求められるのが一般的です。
この際、企業のホームページや公開情報で簡単にわかる内容を質問するのは避けましょう。
企業研究が不足していると判断される可能性があります。
質問の内容は、自分がその会社で働く姿をイメージできるようなものが良いでしょう。
聞きたいことが特に思いつかない場合、以下のような質問を参考にしてください
- 入社後、最初に担当する業務について
- 同じような未経験者がどのようなキャリアを築いているか
- 配属先のチーム体制や雰囲気、出社とリモートの比率
- 採用後に期待される役割や成果について
これらの質問は、企業への興味や自身の成長意欲を伝える良い機会となります。
しっかり準備をして、前向きな印象を残しましょう。
面接に落ちる人の特徴は?
WEBデザイナーの面接は、通過率が決して高いわけではありません。
その中で、面接の評価で落とされやすい特徴には以下が挙げられます。
- 前職の退職理由がネガティブ:批判的な理由や問題点ばかりを挙げると印象が悪くなります。
- 企業研究不足:会社に関する基本的な情報を調べていないと熱意が伝わりません。
- Q&Aのずれ:質問の意図を汲み取れないと、一緒に仕事がしづらいと判断されることがあります。
- 清潔感の欠如:見た目の印象が面接の評価に影響することも少なくありません。
- 受け身な態度:成長の手段を企業に依存する姿勢は、自己研鑽の意識がないと見なされる可能性があります。
特に「研修制度はどうなっていますか」といった受け身な質問は注意が必要です。
企業は労働と対価で結ばれる関係であり、成長は基本的に自己責任と考えられるため、こうした質問はマイナス評価につながりやすいです。
また、不採用の理由には上記以外にも、スキル不足やより優れた候補者の存在、未経験OKの求人の真偽などが影響する場合もあります。
そのため、面接結果を気にしすぎず、次に向けて準備を進めることが大切です。ポジティブな姿勢で自己改善に努めましょう。
未経験でもWEBデザイナーになれるのか?
未経験からでもWEBデザイナーになることは十分可能です。
実際に多くの人がWEBデザインを学び、未経験からキャリアをスタートさせ成功を収めています。
「WEBCOACH」の卒業生も、未経験からWEBデザインを習得し、現在活躍している方々が多数います。
未経験の場合、スキルを効率よく学べる環境や適切なサポートを受けることが重要です。
例えば、ポートフォリオ作成の実践的な指導や、就職・転職サポートを活用することで、スムーズに業界デビューが可能になります。
面接の通過率は?
WEBデザイナーの面接通過率に関する具体的なデータはありませんが、業界の競争率を理解する指標として、厚生労働省が運営する「jobtag」で紹介されている有効求人倍率を参考にすることができます。
有効求人倍率は、「仕事を探している人1人あたりに、どれくらいの求人があるか」を示す数字で、仕事の探しやすさを表します。
例えば、有効求人倍率が1.0の場合、求職者1人に対して1つの求人がある状態を意味します。
一方、0.5であれば、2人で1つの仕事を競い合う厳しい状態です。
WEBデザイナーの有効求人倍率は0.12。
これは、仕事を探している人100人に対して、わずか12件の求人しかないということを示します。
この数値から、WEBデザイナーの求人競争が非常に厳しいことがわかります。
ちなみに、全職種の有効求人倍率は1.29。
この比較から、WEBデザイナーがいかに人気で競争が激しい職種であるかが一目瞭然です。
この現実を踏まえ、しっかりと面接対策を行い、他の候補者との差別化を図ることが重要です。
完全未経験でWEBデザイナーの求人に応募するのはやめてください
未経験からWEBデザイナーを目指す場合、闇雲に求人に応募するのは避けるべきです。
特に「完全未経験OK」と謳う求人には注意が必要です。
未経験OKの求人は怪しいものも多いから危険
「未経験者歓迎」などのタイトルがある求人は多く見られますが、完全未経験者向けの求人は疑いを持ってください。誰でも良いから集めて、WEBデザイン以外の仕事をさせるという求人も多いそうです。
また、採用したものの、記載されていた育成制度などはなく、無理難題を押し付けられることも珍しくありません。
特に数十人規模のベンチャー企業では、そのような体制がないことも多くあります。
入社後すぐに別部署に移動させられ、別業務をさせるという求人も。
実際このような被害意見も出ています。


ポートフォリオがないと採用されないことがほとんど
「未経験者歓迎」という言葉は、スキルや知識がなくても大丈夫ということではありません。
実務経験がなくてもスキルや知識があれば歓迎するという意図が多い傾向です。
そのため、ポートフォリオの提出が求められますが、なければ採用されないことがほとんどでしょう。
ポートフォリオを制作するには、学習はもちろん、架空の案件でも良いので自分でデザインした制作物を載せる必要があります。
未学習者では到底作れません。
スクール卒などの方が良い仕事に就ける
実はWEBデザインの採用担当者の中には、「〇〇スクールの人は安心です」といった信頼関係やパイプがあるケースもあります。
そのため、WEBデザインスクールで学んできたという経験は、非常にポジティブに評価してもらえる可能性が高いでしょう。
未経験からWEBデザイナーへの転職を実現するロードマップ!


面接では、準備していた質問だけでなく、想定外の質問をされることも少なくありません。
そのような時でも落ち着いて対応できるよう、WEBデザイナーになるまでの全体像を整理して理解しておくことが重要です。
また、WEBデザイナーという仕事への理解が浅いと、入社意欲が低いと判断されかねません。
さらに忘れがちですが、面接に合格した後もやるべきことはたくさんあります。
そこでおすすめしたいのが、WEBCOACHが作成した「WEBデザイナーロードマップ」です。
10,000人以上のデータに基づき、面接前に知っておきたいWEBデザイナーの気になるあれこれや、面接までで終わらない、WEBデザイナーになるまでの流れを解説しています。
ぜひ、転職を実現する後一歩のサポートに活用してください。